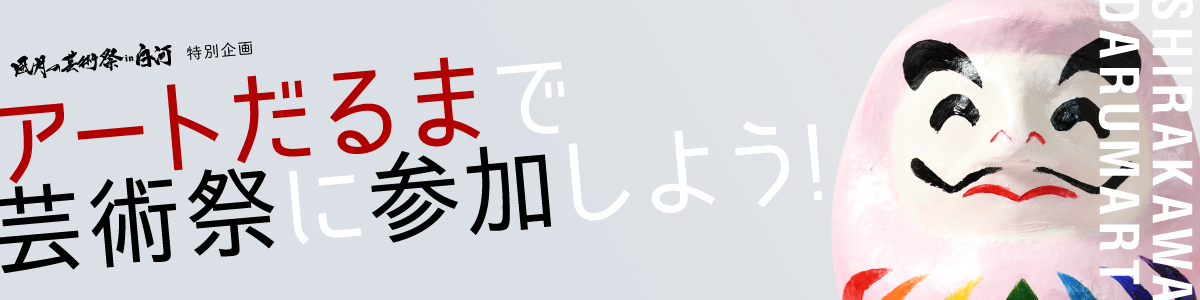版画家
白鴎大学 准教授
齋藤 千明SAITO, Chiaki
近年の制作について
視覚情報だけでは捕捉不能だが、確かにそこに存在するモノを探り出し、それに内在する記憶を五感で捉えて形にしたい。これが制作意図の核であります。
「版表現と身体性」をテーマに表出される作品の形態は平面作品から立体、インスタレーションと様々ですが、主に日本の伝統的な素材と木版画技法を表現手段のベースとし、表層に現れる現象のみでなく対象とどのように関わったか、その過程の形態化をも試みております。
2008年から現在まで続くシリーズ「空蝉のかたち」は、ヒトがいかにもそうであるかのように「よそおう」行為をテーマに伝統的な「紙衣(かみこ)」の技法を用いて自身の服を作り、刺繍や編み物など古くから女性の象徴的な手仕事とされてきた意匠を重ねあわせることにより、心的・主観的形象を微視的に再現した作品です。
作品との偏狭的とも言える関わり方から視点を移行させ展開していくきっかけとなったのが2015年に行ったロサンゼルスでの作品発表であり、初めて訪れたかの地の場景を俯瞰的に眺めていた自分を「雲間から垣間見る」日本美術の伝統的な引き視点を用いて可視化するインスタレーションでした。
現在は、一つの題材に対する関わり方と視点を意図的に変えたものを同一展示空間に投入・構成する異時同図的な表現手法を用いています。
違う環境に身を置き、見て感じたモノをまずは傍観し大局的に判断し、それを自身の領域に持ち帰った時に明確化する感覚的相違を形に表します。
そのためにはフィールドを移動して制作し、それを自分の生活圏内で発表するというプロセスが必要になります。
「他国者」として提示した海外活動と、それを持ち帰りアウトプットする展示を通して鑑賞者との(いわゆるSNS的コミュニケーション形態とは真逆の)プリミティブなつながりが醸成されれば幸甚と活動してきましたが2019年より未だコロナ禍、その制作プロセスが変化してきました。

《シリーズ「水界」より》2019-1〜2021-10
展覧会テーマ:Hydrosphereとは、地球上の水の構成を指す概念「水圏」のことです。「水の守りは万物の生死を分かつ要であり生命の根源」、その水が湧き出る土地には神霊が宿ると信じ、日本では古来より「水」を信仰の対象としてきました。
現在、その「水」と「環境」をめぐっては、さまざまな問題が起こり解決策を見出せずにいます。
日々の生活の中での流れ、渦となり変化する水をめぐるストーリーを具現化しようと試みています。
(現在も制作継続中。最終的に1800×900×40mmのパネル20枚の連作になる予定)
1800×900×40mm×10枚 和紙に水性木版、パネル装 (2021年6月個展 – Hydrosphere – 展示風景)

《空蝉のかたち》2014-1(左衽)
950×610mm
紙衣、和紙に水性木版、コラージュ、モノタイプ

《紙衣》
シリーズ「空蝉のかたち」制作過程
紙衣を着る

《蒼穹渇鴉図-Crow’s eye view of blue sky without water-》
2016年9月 サンタモニカ
18th Street Arts Center インスタレーション
アートだるま展示アートだるまストリートエリア

1966 茨城県生まれ
1989 東京藝術大学美術学部油画科卒業
1991 東京藝術大学大学院美術研究科版画専攻修了
展覧会等
- 2018
- 個展:鹿沼市立川上澄生美術館ギャラリー(栃木県・鹿沼市)
- 2019
- 木版画の魅力-寺田コレクションより東京オペラシティアートギャラリー(東京都・初台)
画中のよそおい 栃木県立美術館 (栃木県・宇都宮市)
Manual transmissions glassbox gallery UCSB(アメリカ・サンタバーバラ)
- 2020
- 個展:殻々工房(栃木県・那須塩原市)
個展:オフィスイイダ企画展(東京・銀座)
- 2021
- 個展:ギャラリーインザブルー(栃木県・宇都宮市)
- 2022
- [TANAGOKORO]ロサンゼルス国際交流基金ギャラリー(アメリカ・ロサンゼルス)
受賞歴
- 2003
- Asian Artists Fellowship The 8th Annual Freeman Foundation VSC 受賞
- 2004
- 第10回川上澄生美術館木版画大賞展 大賞 鹿沼市立川上澄生美術館(栃木県・鹿沼市)
- 2009
- 第22回全国和紙画展 アート部門 大賞 美濃市和紙の里会館(岐阜・美濃市)
- 2015
- 第28回全国和紙画展 アート部門銀賞、 和紙画部門銀賞 美濃市和紙の里会館(岐阜・美濃市)